

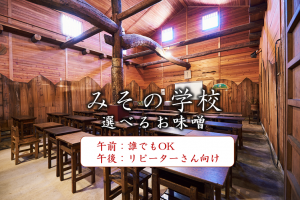
2019年4月度の「みその学校~手作り味噌教室」の開校日が4月20日(土)に決定!
今回は初開催のリピーターさん向けのクラス(蔵歩きやみその勉強は無しで、仕込みに特化)もあります。
そして、蔵歩き(見学)は桝塚味噌3代目、みそ仕込みは4代目が担当するちょっとだけスペシャルな月です!
みそについて学んで実際にみんなで手前みそを仕込みましょう!
内容・申し込み 詳細は「手前みそのススメ」で検索してください。
https://temaemiso-susume.com/event/1362/
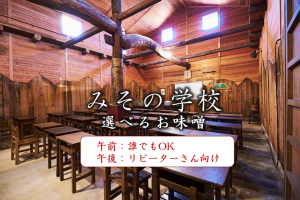
2019年4月度の「みその学校~手作り味噌教室」の開校日が4月20日(土)に決定!
今回は初開催のリピーターさん向けのクラス(蔵歩きやみその勉強は無しで、仕込みに特化)もあります。そして、蔵歩き(見学)は桝塚味噌3代目、みそ仕込みは4代目が担当するちょっとだけスペシャルな月です!
みそについて学んで実際にみんなで手前みそを仕込みましょう!
*豆みそと米みそから選べます!
発酵や味噌作りに興味ある大人の方はもちろん、お子様と一緒に自分たちの手で大豆を潰して味噌を仕込むという貴重な体験をお楽しみ下さい。
また通常では見る事のできない貴重な味噌蔵や江戸時代から使われている150年以上前の木桶など、実際に味噌を仕込む蔵を見ることもできます。
内容・申し込み 詳細は「手前みそのススメ」で検索してください。
https://temaemiso-susume.com/event/1362/
有ること難し。 店主
先日行われた愛知県味噌溜醤油品評会で弊蔵の豆みそを使用した「木桶熟成赤だし」が1品のみ選ばれる最高位である知事賞をいただきました。
木桶や蔵、そこに住む微生物たちに感謝を忘れず、
自分たちが表現したい味。
食べる方が感じる味。
これからも主観と客観のバランスを考え、整えながら美味しいお味噌を育てていきたいです。
撮影者が社長かつ慣れない場の為、代表して賞状を受け取った近藤君の笑顔が少しひきつってますね。
有ること難し。 店主
11年目、後期の椙山女学園大学教育学部の授業です。
恒例となった野崎教室の見学会、将来教師を目指す皆さんに期待を込めて開催しています。