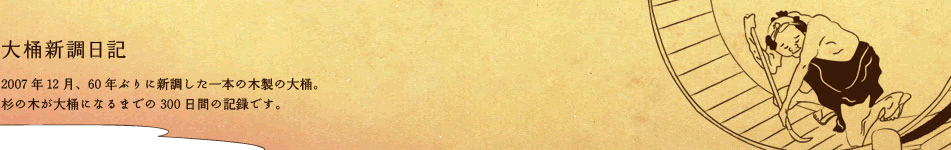
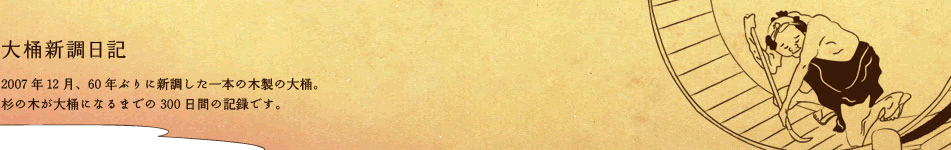
野田味噌商店さま
昔、大正時代のことです。
奥三河の山師が、杉の苗木を背負って山を登り、地をほって、一本植えては土をかぶせ、ただひたすらにそれを繰り返し、沢山の杉の木を植えました。一町歩の面積に植えられたその数、およそ二千五百本。
山師はその翌年、夏の暑い日差しが照り付ける中、鎌を持って山へ行き、苗に覆い被さる雑草を何日もかけて刈りました。
その翌年も、その又翌年も・・・。
五年経つと、杉の苗は人の背丈ほどになり、雑草にも負けないくらい大きくなりました。
十年経つと、杉の木は人の背丈の倍もの大きさになりました。
成長が悪く枯れてしまいそうな木を、五百本ほど伐りました。
二十年経つと、隣の杉の枝がのびてきて窮屈になったので、曲った木、傷のある木を五百本ほど伐りました。
三十年経った時、さらに五百本ほどの木を伐りました。
五十年経った時、さらに五百本ほどの木を伐りました。
そして残った五百本の木が、ただひたすらに大きくなるのを待ちました。
苗を植えた山師たちは、皆この世を去っていきました。
山を受け継いだ者も、ずいぶんと歳を取りました。
そして九十年が経った時、杉の木は、下から見上げるとてっぺんが見えないほど大きくなっていました。
伐採の時を迎えました。
平成十八年の冬、五百本の木は、すべて伐り倒されました。三ヶ月間、凍えそうな山で葉枯らしをした後、少し暖かくなりはじめた村まで運び、製材をしました。
味噌桶に使える杉の丸太は、五百本の木からおよそ八十本取れました。太さ、色合い、節の大きさ、運ばれた八十本の丸太から、一丁の大桶になる材料を作りました。
その材料たちが加工され、組み立られ、ここに味噌桶となり置かれています。
小さくなってしまったね。でも、よかったね。これから、幾世代も、味噌を守ってくださいね。あなたの中でひとなった味噌は、沢山の人を幸せにするからね。
有ること難し。 店主