



味噌の仕込み終わった大桶は、数日間の慣らしを終えた後、
麻布を敷き重石をします。
簡単に見える重石置きですが・・・
昔から「重石置き、5年。」と蔵では言われています。
重石を理解するのも5年はかかると言う意味です。
桶の大きさ、石の大きさ、そして重さなど、毎回違います。
すべて桶、味噌そして重石の気持ちが判るようになると、
石を持った瞬間に、仕込みの済んだ桶の「ここ。」に
こんな感じでと・・・石が教えてくれるそうです。
いや、「石が教えてくれるような気がします。」
合掌。 店主

味噌の仕込み終わった大樽は、表面を丁寧に均(なら)します。決して、すぐに重石は置きません。
まず、諸味(もろみ・仕込みの済んだ味噌)を新しい環境に、慣らすのです。
「どんな生き物でも、急激に環境が変わると、
ストレスが貯まり体力が弱りますよね。味噌も同じなんですよ。」
ですから、数日間は静かに大樽の環境に慣らすのです。
「味噌は、作ってはいけない、育てるんだ。」
先輩たちの、言葉が脳裏に浮かびます。
合掌。 店主


蔵の中には約400本の大樽があります。
洗いの済んだ大樽に、製麹の終わった味噌玉、塩そして水を混合し仕込みます。
大樽は10トン〜20トン入ります。
樽の周囲は、蔵人により丁寧に、踏み込みをします。
(均等に、そして空気が入らないように、スコップ片手に行います。)
薄暗い樽の中は、まだ味噌の香りはありません。
ただ微かに、麹の香りが漂います。
「ザッ、ザッ、ザッ。」と踏み込みの音だけが、樽の中に残ります。
18ヵ月後まで、出来上がるのを楽しみに、
静寂の中、作業は続きます。
合掌。 店主


種麹を付けた味噌玉を、3日間かけて製麹(せいぎく:麹菌を培養し、繁殖させること)温度、
湿度管理を行いながらします。
昔は、屋根裏でむしろを使いながらしました。
当時は温度調節が難しいため、夏場はできない工程でした。
冬場の気温の低い時期だと、温度管理もでき、いい麹ができるため、
「寒仕込み」という言葉は、今でも味噌、醤油そして清酒造りに
よく言われます。
蔵人は味、そして香りで味噌玉の状態を判断します。
「とても気を使う瞬間なんですョ。」
合掌。 店主
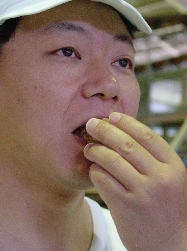

原料処理の終わった大豆は、浸漬そして蒸煮(じょうしゃ)されます。
そして女性のこぶし大の玉にします。このことを蔵では、玉握りと言います。
蔵では、「一水、二焚き、三麹。」と言われ、昔から一番気を使う工程です。
最新の設備で管理されていますが、やはり蔵人の勘が重要です。
触り、実際に食べ判断します。
「やはり、この地元の大豆は甘味がある。」と蔵人。
このひとことに職人の自信を感じます。
「いい味噌になれよ。」と蒸したての大豆に言いたくなります。
そして、表面に種麹をまぶし、3日間の製麹をし、十分麹菌を育てます。
さあ、次は仕込です。
合掌。 店主