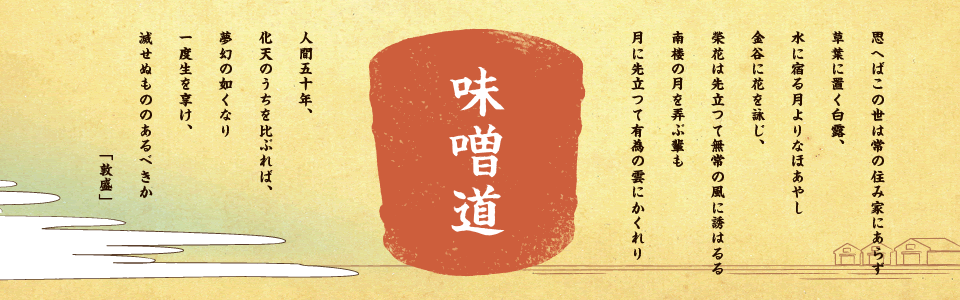
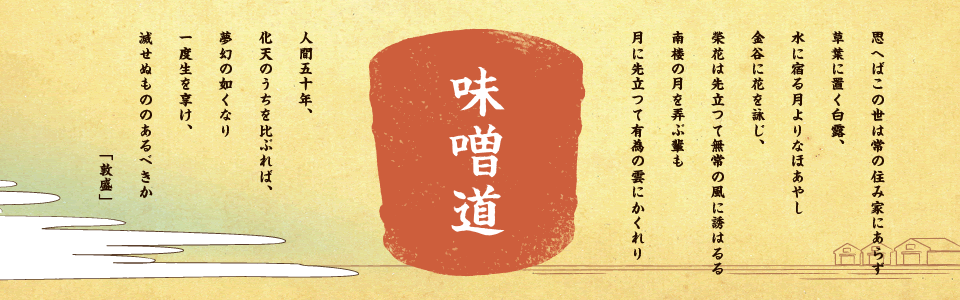
2020年04月01日
みなさんこんにちは
卒業式の季節ですね。
今月でブログを始めて1年になりました!
初めのうちは、自ら発信することに慣れていなかったためぎこちなさもあったと思います。
しかし、写真のクオリティも少し上がり、皆さんに上手く伝えることができたのかなと感じています。
今までご紹介してきた味噌の作り方や出し方などは、だいぶ慣れてきたものの
まだまだ知らないことも多く、学ばなければいけないことがたくさんあります。
先輩方がやっている作業を私1人でもできるようにするのが目標です。
また、大豆から味噌を作るまでの作業だけではなく、
みその学校という人前で話す機会もいただけたおかげで桝塚味噌のことだけでなく
広く知識を得ることの大切さを学びました。
人に伝えることの難しさも改めて実感したので、より分かりやすく伝えられることのできるようにしたいです。
このブログを書くことで、今までやっていた作業を振り返り、
その作業を一番分かりやすく伝えるにはどの場面を写真に収めればいいのか?
短文かつ接しやすい文章で伝えるにはどのように書いたらいいのか?など
今までにない視点で考えるという貴重な経験ができたと思います。
今月で私のブログは終わらせていただきますが
今後、桝塚の味噌を食べる際には私たちが頑張って作っていることを少しでも思い出していただけたら幸いです。
また、みその学校に来ていただければいつでもお会いできますので、ぜひお待ちしております!
2020年02月27日
みなさんこんにちは
寒さも少しずつやわらぎ、日も長くなってきました。
今月は「みその学校」についてご紹介します。
「みその学校」とは、蔵見学やみその勉強を行い、最後にご自分で味噌を仕込んでもらう…
というイベントです。
最近では、すぐに予約でいっぱいになってしまうほどご好評をいただいています!
さて、この「みその学校」の準備を主に私が行っています。
まず豆味噌は、味噌玉を取るところから始まります。
直近の仕込みの日に、コンベアの横で玉を拾っていきます。
この時、水分の量などを計算して、どれくらいの量の玉を取るかを決めます。
皆様に楽しんでもらえるよう、少しでも大きくきれいな玉を取るように心がけています。
流れてくる玉を見すぎて目が回ることもしばしば。
次に塩や米麹、容器などはあらかじめ前日に準備しておきます。
そして「みその学校」の当日
最近では、学校内の味噌についての説明の部分を喋らせていただいているのですが
まだまだ至らぬ点も多くあるので、なんとか楽しんでもらえるように日々ネタを集めています。
また、他の味噌屋さんでの仕込み体験での話や、他の地方の味噌の話など
お客様との会話を通じて新たな発見もたくさんあり、とても楽しませていただいてます!
いつか社長のように味噌愛に溢れた深い話ができるよう、日々精進しようと思います!
2020年01月18日
遅くなりましたが、あけましておめでとうございます!
今年は去年よりももっと学びの多い1年になるように頑張りたいと思っている夏子です。
さて今月は「たまり」についてご紹介していきます。
たまりと言っても、桝塚味噌には「本溜」や「たまり醤油」などの種類がありますが
、こういった商品の原料になっているのが豆味噌の味噌出しの工程で取れる『みそだまり(上溜まり)』というものです。
簡単に作り方としては味噌の上から採れる「みそだまり」を元に、味噌や塩を入れたものを小さな木桶に入れ、蒸気で煮ていきます。
それを人の手で丁寧に布袋に入れていって濾過します。
この濾過する袋を持つ作業ですが、この醤油が煮えたばかりなのでとても熱く、
作業全体の後半に差し掛かると、集中力が切れて手にかかったりするときがあるので、緊張感ある作業です。
上に重しの役目となる木を載せて濾過していきます。
この木も、見た目に反してとても重いため私一人では到底持ち上げられません。
そんな木を4,5本載せてじっくり時間をかけて濾過します。
そして下から出てきた醤油をザルで濾したらできあがりです。
これらをさらに加熱殺菌してから商品にしていくので、
時間と手間がとてもかかっていますが、その分深みがあっておいしいたまり醤油に仕上がります。
『たまり醤油』は、ぜひ煮物の味付けやカレーの隠し味などに。
『本溜』は、最高級のお塩のようにお肉や魚に少しつけて。
私は最近はこのたまり醤油で炒飯を作るのにハマっています。
では、来月は「みその学校」の裏側についてご紹介します!
2019年12月17日
こんにちは
だんだん寒さが厳しくなっていますね
さて、前回は米味噌を仕込んで、踏み込むところまでをご紹介しました!
踏み込みを続けながら、桶の8分目ほどになったら、表面の空気を抜いて
塩を振ります。
そして重石を載せていきます。
豆味噌と違い、重石は表面が埋まる程度の1段しか積みません。
というのも、豆味噌と比べて桶が小さいことや水分が多く柔らかいかいため、多くの重石を載せなくても上手く熟成するそうです。
米味噌は、豆味噌と違って熟成期間は短いですが、
気温などによって、出来上がりが左右されやすいので
旨味が出ているかどうか、色合いはどうかなどを定期的に確認しながら
味噌を出す時期を決めていきます。
熟成し終わった白味噌は、全て手で掘り出していきます!
黄金色で美味しそうですね。
味噌出しをした後、使いやすいように摺り機で粒をなくしたり、合わせみそに使ったりしていきます。
さて、私が入社してすぐに仕込み体験で仕込んだ豆味噌が出来上がりました!
淵には産膜酵母という白いカビが生えているので、それを丁寧に取り除き、
カップに詰めました。
アミノ酸の結晶である「きび粒」が少し多いですが、舌触りや味も滑らかで、塩角も少ないおいしい味噌になりました!
さっそく家でサバの味噌煮を作りましたが、味噌を多めにしたにもかかわらず
全くしょっぱくなく、半身をぺろりと平らげてしまいました。
また機会があったら仕込んでみようと思います!
2019年11月13日
こんにちは!
いよいよ寒くなってきました。
豚汁がおいしい季節です。
前回までは、豆味噌について紹介してきました
今回は、米味噌が仕込まれるまでについてご紹介していきます!
米麹は、蒸したお米に菌を付けて、4日ほど室に入れます。
そして、出来上がった米麹を水煮大豆と混ぜていきます。
そこに塩と水を加え、混ぜます。
木桶に入れる前に、5㎜の網で摺っていきます。
というのも、豆味噌では豆麹をつぶしていました。
米味噌でも、発酵を促すために、摺り機を使って細かくしてから仕込んでいきます。
そして豆味噌と同じように、空気を抜くために丁寧に踏み込んでいきます。
豆味噌の踏み込み作業も大変と以前お伝えしましたが、
米味噌の際も同じく大変です。
今回の仕込みでは、特に柔らかく、どのくらい埋まるかといいますと・・・
これが足を着けた状態。
体重をかけると、くるぶしを越えて足首まで一気に沈みます。
沈みながらも、コンベアから次々流れてくる米味噌を平らにして
踏み込まなければいけません。
初めて作業したときなどは、酷い筋肉痛になっていました。
さて次回は熟成からみそを出すところまでをご紹介しますね!