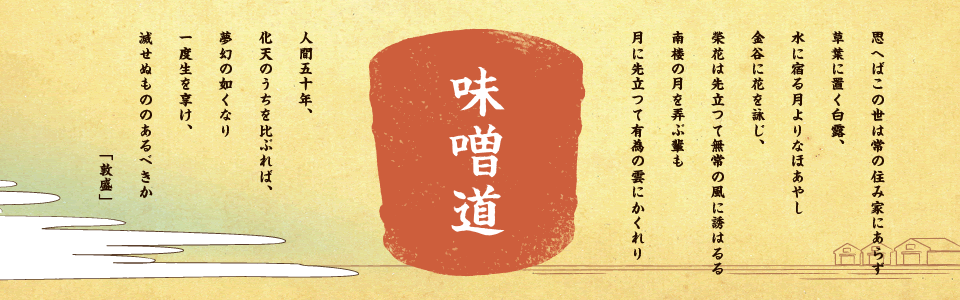
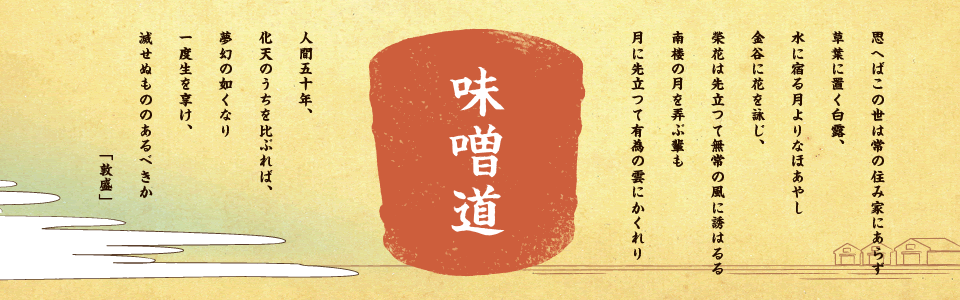
2019年07月16日
こんにちは!
冷やし中華はゴマだれ派の夏子です
前回、大豆に菌を付け、室(むろ)に入れて…
あれから2日後!
全体が真っ黄色に!
この黄色は全部菌が頑張って増えた結果です。
「みその学校」に参加したことある人は見たことがあると思います。
さあ、今回は仕込みについて紹介していきます!
先ほどの黄色になった玉を「みそ玉」と呼んでいます。
このみそ玉を、砕いて
塩と混ぜて
水も加えます。
こうしてできた味噌のもとを約500㎏づつ、48回ほどに分けて桶へ入れていきます。
毎回入れた後、スコップで均して
空気を抜くために人が入って踏んでいきます。
これが大変!
大豆の乾燥具合によって、加える水の量が変わっていきます。
加える水が多い日の踏み込みは、田んぼに足を突っ込んだような感じになり、
はまって動けなくなってしまったり、長靴が脱げそうになったりします。
入った当初は、仕込みの翌日は必ず筋肉痛になっていました。
味噌のもとを入れ終わったら、数日寝かせて、塩をまんべんなく振って
重石を載せていきます。
このとき上手く並べられるようになると「石の顔がみえてくる」と、聞きましたが
「石の顔」はいまだにわかりません。
マジックペンで石に顔を書いてほしいぐらいです。
毎月恒例の大豆はどうなっているでしょうか?
花が咲いていました!
定期的に雑草を抜いたりしたおかげでしょうか。
大豆の花って、紫色なんです!
そして枝分かれした間に咲くため、上から見ただけでは花が咲いているかわかりません。
みなさんも大豆畑を見つけた際などは少し下から見てみてください。
来月は、みそを熟成させている木桶についてご紹介します!
2019年07月06日

2016年から始めた木桶再生プロジェクト。
16年は、自分の結婚式で木桶材からリサイズした100年木桶作り
17年~18年は、東京に木桶のエントランスを作ったTokyo Barrel
そして今年は、ついに温めていたプロジェクトその名も
『Wood Board』を開始します!
ブログ https://temaemiso-susume.com/kioke-project/1837/
有ること難し。 店主
2019年06月20日

こちらのクラスはみその教室に参加した事があるリピーターさんや夏休みの自由研究でみそを仕込みたい親子向けのクラスです
過去にみそ教室に参加された方向けのお得なリピーター教室が7/20(土)PMに開催決定です!
〇違う種類の味噌を仕込んでみたい
●細かい味噌の知識はOKだから仕込みだけやりたい
〇こだわった道具で仕込んでみたい
●もっと量を仕込みたい
前半のみそのキホンやテイスティングなどのパートは省略して、前回話していない麹の話をした後にみその仕込みにすぐ取り掛かります!
ご自身のペースとこだわりで仕込んでいきましょう!
*容器を持っていない方は容器を選んで下さい
*量と種類も調整可能
仕込む味噌は、熟成期間が短めの米みそ(白みそ)と長期熟成型の豆みそ(赤みそ)からお好きな味噌を選んで下さい!
容器がある方は、もちろん持ち込んで再利用、更にこだわりたい方には専用の道具もご用意します。
ぜひ楽しくみそを仕込みましょ!!
内容・申し込み 詳細は「手前みそのススメ」で検索してください。
https://temaemiso-susume.com/event/1801/
有ること難し。 店主
2019年06月20日

東京・代々木での2019年7月度の手前みそ教室の開催日が決定
7月の開催日は・・・お子さんは、夏休みに入っている7/20(土)になります。
*大人の方のみ参加できるクラスです
仕込んでいただく味噌は、熟成期間が短めの米みそ(白みそ)と長期熟成型の豆みそ(赤みそ)からお好きな味噌を選んで下さい!
特に東京で本物の豆みそ(赤みそ)の仕込みが体験できるのは、間違いなくここだけです!
発酵に興味がある方、手前味噌を仕込んでみたいと思っていた方など、作り方からお家での保管方法まで詳しく丁寧にご説明させていただきます。
ぜひ楽しくみそを仕込みましょ~!!
内容・申し込み 詳細は「手前みそのススメ」で検索してください。
https://temaemiso-susume.com/event/1794/
有ること難し。 店主
2019年06月14日
こんにちは!
暑くても味噌煮込みうどんがやめられない夏子です。
前回は、大豆を蒸すところまでをご紹介しました。
今回は、蒸した大豆に菌をつけていく工程です!
大豆は煮ると乾燥大豆と変わらない色ですが、蒸すと色が赤くなるんです!
初めて知った時はとても驚き、感動しました
これを機械で、ところてんのように押し出された蒸し大豆をカッターで切っていき、こぶしほどの大きさ(これをみそ玉と呼びます)にしていきます。
そして、その玉に豆味噌専用の麹菌(種麹)をつけていきます。
このように、コンベアで流れてきた蒸し大豆に、菌をまんべんなく降りかけられるように
出す量を調節します。
菌を付ける前と、付けた後がこんな感じです!
初めのうちは、慣れてないせいで菌を吸ってむせることや
粉を出す量の調節がうまくいかなかったり、詰まらせてしまったりなど、いろいろな失敗がありました。
本当かどうか定かではないですが、麹菌をまぶす係をやっていると肌がきれいになるとか。
以前ここを担当していた社員は、そのおかげか、肌がきれいだと医者に褒められたらしいです。
きっと肌がきれいになってくれることを励みにこれからも頑張っていきます。
さて、菌をまぶしたら、次は室(むろ)にいれます!
ここでは温度を一定にして、2日(約48時間)かけて菌を増やします。
これは室の中で均等に並ぶように調節しているところです。
2日後、どうなっているかはまた次回にご紹介しますね!
そして皆さん、覚えているでしょうか。
前回土に埋めてみた大豆を。
見事、芽が出ました!
2週間ほどで本葉まで出てくれました。
この調子で、次は花を咲かせるぞ!
それではまた来月!