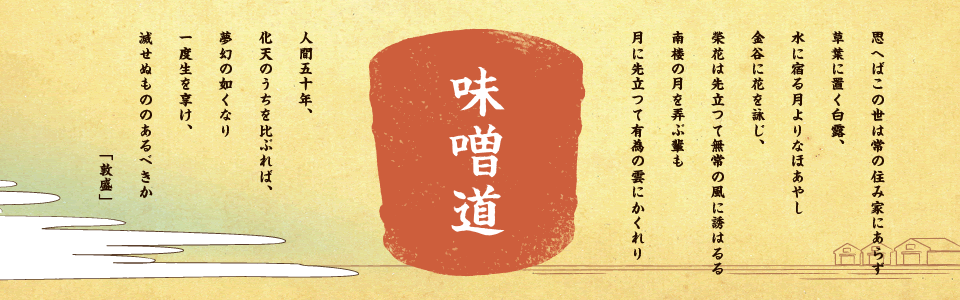
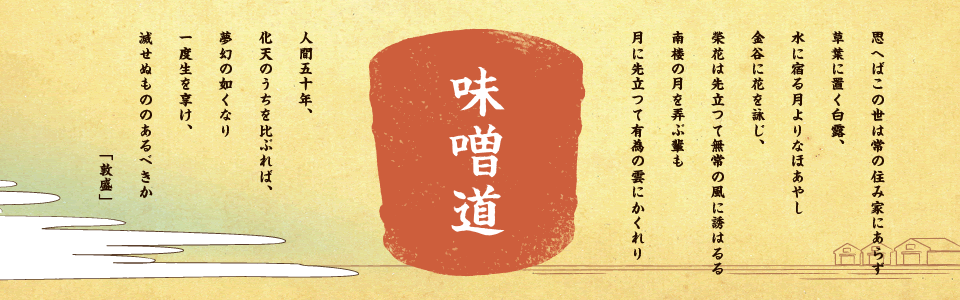
2021年01月21日
新年あけましておめでとうございます
今年もよろしくお願いします
私は野田味噌商店で味噌の製造責任者をしています
『蔵 頭』
の高橋です
今回は桶についてお話します
桶といったら
みなさんはどんなイメージを持ちますか
材質は木で・・・
大きさは大人の2倍以上で・・・
私たちが仕込みに使っている桶は
もちろん 材質は木です
木の種類はと言うと『杉』の木を使用しています
杉の木は 水や害虫に強い事
日本には杉がたくさん育っていたことが関係しています
蔵頭は
花粉症のため
憎たらしい木ではありますが
桶には何の落ち度もありませんから許してあげましょう
木桶の大きさは2m50cm
ジャイアント馬場が入っても隠れてしまいます
アンドレ・ザ・ジャイアントもギリギリ隠れますね
今で言うと 八村塁も隠れます
*ジャイアント馬場 209cm アンドレ・ザ・ジャイアント 224cm 八村塁203cm
そんな大きな木桶が日本全国の味噌屋で使われているかと
思われがちですが・・・・・
実は違うんです
日本には数千件の味噌屋さんがありますが
木の桶を使って製造されている味噌に量は
全体の
5%
しかないんです
因みに
ほとんどは金属(ステンレス)の桶で醸造されています。
しかも
2mを越える大きな木桶は数件でしか使用されていません。
こんな貴重な大きな桶
蔵には桶がこれ以上置けないくらい置いてあります
是非 見に来てくださいね
次回も 桶の話し Part2 です
山口百恵は
そう
プレイバック です
有ること難し。 店主
2021年01月12日
2021年01月07日

コロナ対策として、通常より人数を減らしての開催になります
2021年2月度の開催日は、@名古屋/金山2/13(土)、@桝塚味噌2/20(土)、@東京/代々木2/21・28(日)になります。
仕込んでいただく味噌は、熟成期間が短めの米みそ(白みそ)と長期熟成型の豆みそ(赤みそ)からお好きな味噌を選んで下さい!
特に東京で本物の豆みそ(赤みそ)の仕込みが体験できるのは、間違いなくここだけです!
発酵に興味がある方、手前味噌を仕込んでみたいと思っていた方など、作り方からお家での保管方法まで詳しく丁寧にご説明させていただきます。
ぜひ楽しくみそを仕込みましょ~!!
2021年 2/13(土)味噌作り教室@名古屋/金山
内容 申込みhttps://temaemiso-susume.com/event/3323/
2021年 2/20(土)味噌の学校~味噌作り教室@桝塚味噌
内容 申込みhttps://temaemiso-susume.com/event/3314/
2021年 2/21・28(日)味噌作り教室@東京/代々木
内容 申込みhttps://temaemiso-susume.com/event/3307/
2021年 2/28(日)リピーター向け味噌作り教室@東京/代々木
内容 申込みhttps://temaemiso-susume.com/event/3309/
有ること難し。 店主
2020年12月22日
みなさん
すっかり寒くなってきましたが
如何お過ごしですか
野田味噌商店の
『蔵 頭』
高橋です
今回は
味噌の仕込みについてです
仕込み?
酒造りの世界では寒仕込みといって
寒い時期に仕込みをおこなっていますね
これは
寒い時期だと「雑菌が少ない」、「温度を下げるのが容易なこと」が理由です
*最近は管理能力が上がった影響もあり通年で仕込む酒屋も増えてきましたが
ただ私たちは味噌の仕込みは1年中おこなっています
味噌屋になる前は酒造りをしていたので最初びっくりしました。
理由は
味噌の品質(味・香り・色)は
熟成によって違いが出ます
今年は寒いから仕込みを1ヶ月やめたとします
月日は流れ 2年後 味噌を出荷する時に前回出した味噌と今回出した味噌
1ヵ月も熟成期間が違うと全然違う味噌になってしまいます。
同じ商品なのに色が違ったり 味が違ったり・・・
すごく美味しい味噌を造るのは目標でもあります
でも
食品メーカーとして
たまに美味しいものを作るのではなく
常に安定して、美味しい味噌を作らなければなりません
NO.1ではなくて only one です
みなさんに安心して食べてもらえるように
これからも味噌を造り続けていきます
味噌造りには終わりがないんです
この地方は三河なので尾張ではないですが・・・
次回は仕込みに使われている 木桶についてお話しますね
OK(桶) ですか?
では 次回お楽しみに!
有ること難し。 店主
2020年12月10日