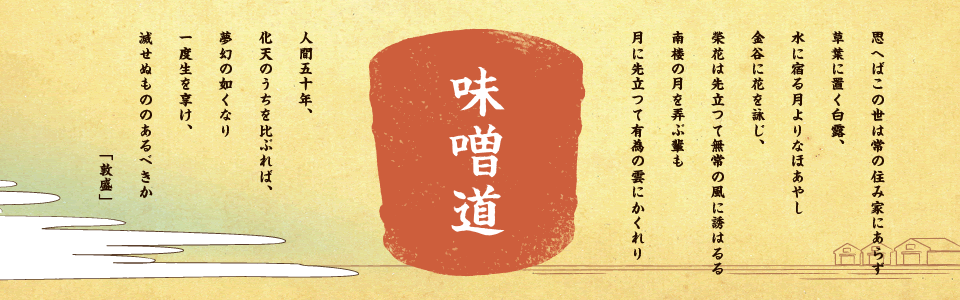
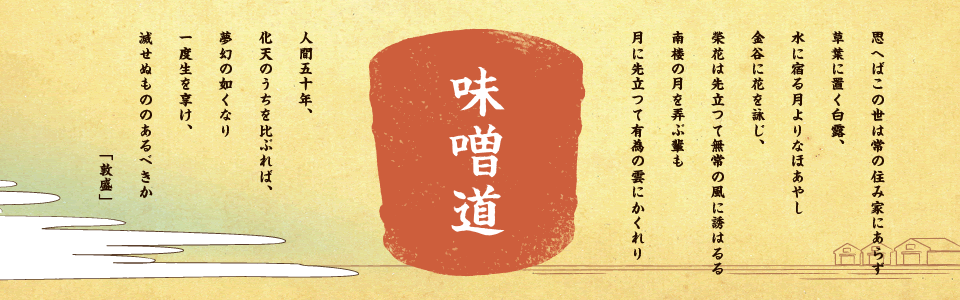
2001年06月10日


中国の個人農家では、まだ牛馬に頼った農作業をしていますが、
この引龍河農場では大規模機械化が進んでいます。
年間25,000tの大豆を生産し、輸出は5,000tです。
選別も機械化され、圧搾製油工場もあります。
農民の生活水準は、1月5,000〜6,000円程度の所得で、
農場長の祝さんは「この農場の農民は、とても幸せです。」
と胸を張ってみえました。
そして、遺伝子組み替えの大豆については、絶対にあり得ない事、また、してはいけないとの、言葉が印象的でした。
農場からの帰り道、通訳の張君は
「確かに、この農場は規模、レベルともに良い方です。」
一般の農民は、もっと低い生活環境にあると、説明してくれました。
確かに、この農場に来る途中の農家は、土壁の藁葺きの家が多く、ロバ、馬そして牛による農作業を多く目にしました。
自由経済が、共産主義の社会で、貧富の差を広げているのは確かです。
「筆重く 瞼も重き 遠蛙。」
辰
2001年06月03日

植木屋

朝市の人々

麺屋

民族舞踏
黒龍江省北安市。
接待所(宿泊所)の風呂のコックをひねると、赤黒い水です。
その赤黒い水は、体を洗っているのか、汚しているのか判りません。
シャワーの水を顔に当てて、冷たい澄んだ水を想像します。
石鹸を使うと、体の汚れか水の汚れか、判らない色の凝固した泡が足元に貯まります。
日本で当たり前のきれいな水は、ここではカバンのミネラルウォターだけです。
朝市は、40万人の町を感じさせてくれる場所です。
数百メートル続くメインストリートには、毎朝5時から9時ごろまでは人、人、人。
「どこから来ているのだろう」と感じるくらいに、人間の生活の営みを感じます。
どの顔も、たくましく、黒く、女性でも化粧化はありません。
雑貨、饅頭、麺、パン、たばこ、下着、石鹸、野菜、米、床屋、医者、植物、菓子屋、
中華風お好み焼き屋、服屋、ともかく臨時路上百貨店の様な様子です。
そして自転車を押すおじさんの首から、職を求めるため「塗装。」「修理。」「工事。」と赤い文字で書かれた看板が、目に焼き付きました。
また、職を逃したようです。
「取替えて 着るも短し 宿浴衣。」
辰
2001年05月29日

北安駅前

朝市の豆腐屋
ハルピン市から北へ、305kmの北安市の招待所が今回の農場視察の宿泊所です。
この町は、40万人の人口を抱え、戦争中はあの有名な731部隊の基地もあった場所とのことです。
数年前、民家の庭から旧日本軍の化学兵器が出てきて、
日本政府がその処理を行いました。
そして、北安の病院にMRIの医療設備を送ったそうです。
なかなか、戦争の傷は消えませんが、時間と努力が必要です。
通訳の張君が
「戦争で傷付くのは、いつも民衆です。中国も日本も同じです。」
という言葉に、少なからず救われた様な気がしました。
当時の731部隊の建物も現在学校として使われています。
その言葉に対し、
「我々の味噌蔵も、戦争中の海軍飛行場の格納庫が、蔵として使用されています。」
なぜか、自慢してしまいました。
「若葉風 民芸調の 椅子にかけ。」
辰
2001年05月24日
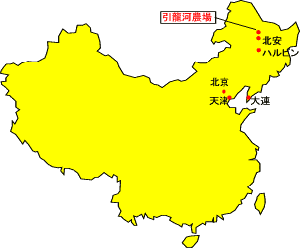

満州道は、時速120キロで、北へ真っ直ぐ延びる。
幾重にも続く、大地の波の頂上を越えると、
その先に、また新しい波が現れる。
変化の遅いとか速いは、在るにしても、やはり大地は海と似ている。
両側のポプラの街路樹は、
若葉をつけ、すこし頭を東に向けている。
風と地球の自転を感じる。
左右の大地は、芽を吹いた小麦畑と黒い大地が、現れては後ろに飛んでゆく。
なぜか、人間の小ささを感じてしまう。
大きな自然を見つめると、
自分の小ささを感じるのは、小生だけではないでしょう。
「龍天に 祭太鼓の 満州路。」
辰
2001年05月20日


長年、味噌と共に生きてきた小生も初めて、蔵で使う「中国産大豆」の産地を見に行く機会をえました。
行き先は旧満州、黒龍江省ハルピン市の北400kmにある引龍河農場です。
あと200kmでロシアとの国境です。
はじめての日本人という事で、農場サイドもビデオ撮影とやや緊張気味でした。
農場といっても3,600k㎡の面積と、11,000人の農民を管理する、日本では想像できない規模です。主要作物は大豆と小麦です。
まず招待所で農場長の祝 殿凱氏より概略説明を受け、歓迎の意を表されました。
そして、すぐに大豆播種の現場、農業機械置場、選別場、貯蔵庫と見て回りました。
地平線まで続く、波打つ黒い大地。青い空。
舞う土埃。逃げ場の無い西風。道路脇にポプラの街路樹。
まさに、大地です。
「御土産に 小さき壺の 新茶買う。」
辰
110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129